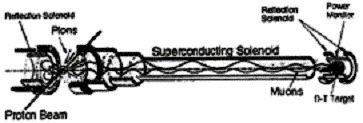核融合は、二つの水素同位体(重水素Dや三重水素T) の原子核を10-12~10-13cmの距離まで近づけると核力により融合する反応である。この際に、二つの核が同じ正の電荷を持っているために、電気的な反発力を及ぼし合い近づくことが出来ない。いわゆる高温(熱)核融合では、二つの水素同位体核を1億度を越える高い温度に熱することによって、熱エネルギーの助けを借りて核を近づけることをねらう。これに対して、電子より207倍も質量の大きい負の電荷を持つ負ミュオン(µ-)を導入して、二つの水素同位体核の一つにまきつかせ、通常の水素原子の1/207のサイズを持つ中性原子をつくると、電気的反発力が消失し、二つの核が容易に近づき、高温を必要とせず、核融合反応が起こる。
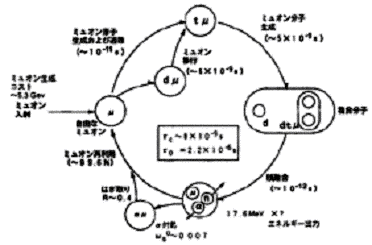
(液体水素密度、トリチウム濃度30%の場合)
ミュオン分子 (dtµ)の基底状態の大きさは5×10-11cmで、核力の到達距離の100倍程度であり、分子振動の助けを借りて分子内で核融合が急速に (10-12秒以下)起こる。その結果、中性子とα粒子とが発生するが、自由になったミュオンはまた次の反応へと向かう。かくしてミュオンは次々と連鎖的に核融合を起こしエネルギーを発生する。以上がµCFの原理である(図1)。
ミュオンの寿命2.2マイクロ秒の間に、何回核融合が起こるかについては、融合反応後に生まれるα粒子にミュオンが付着する割合、アルファ付着率で決まる。後に述べるように、固体又は液体のD-T標的(T濃度:40%)中でミュオン1個当たり150回以上の核融合を起こし、アルファ付着率は0.4%程度と測定されている。この結果ミュオン核融合によるエネルギー生産の上限が決まり、ミュオン1個あたり4GeV(250回の核融合×17.6MeV)となる。アルファ付帯率をいかに減らすかが、エネルギー生産性向上の当面の課題となる。
高強度・高エネルギーの陽子や重イオンをBeやLiなどの原子核にあて、パイオンを生み、それが崩壊してミュオンが生まれる。原理的には1GeVの重陽子から0.20〜0.25個のµ-を生み、利用することができる。つまり、1個のµ-を生むのに4〜5GeVのエネルギーが必要となる。これまでの実験結果は、ブレークイーブン条件のごく近くまでゆけることを意味する。
このようにミュオン核融合は加速器駆動型である。従って、加速器を止めれば核融合は止まり、加速器が動き続けるかぎり核融合は起こり続け、“暴走”することはない。
英国の理研-RALミュオン施設で行われた理研-KEK-東大理-原研-電総研-RALグループの実験には、次の大きな特徴がある。;
1996年から開始されて、現在進行中の理研RALミュオン施設におけるミュオン触媒核融合で明らかになった点を以下にまとめる。
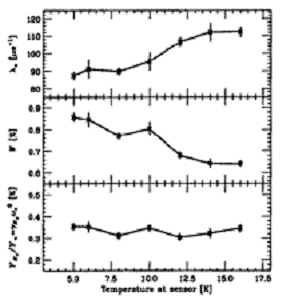
加速器からのビーム強度をさらに増すことにより、ミュオン核融合からさらに大きなパワーを生みだす。21世紀に展開されるであろう「大強度破砕中性子源」「ニュートリノ・ファクトリー」、「ミュオン・コライダー」などに先導された加速器計画のなかで、ミュオン核融合研究が進展する。
現時点での予測を以下にまとめる。
(1) KEK-原研「ハドロン統合計画」におけるミュオン核融合
KEKと原研の間で計画が進められている大強度陽子加速器計画では、第I期に3GeV330μA(1MW)の陽子ビームが、第II期では5MWの陽子ビームが得られる施設を原研東海研究所内に建設することを計画している。これらのビームを利用すれば、高出力のミュオン核融合の実現が期待される。第II期計画では、数100kWクラスのミュオン核融合炉の実現が可能になる。
(2) 専用重陽子加速器におけるミュオン核融合
ミュオン核融合に用いられる負ミュオンはビーム中に“中性子”を内蔵する重イオン加速器のほうがより効率よく、ミュオン核融合を起こすことができる。1GeV、10mAクラスの超伝導重陽子加速器がMWを超すミュオン核融合炉にとっては理想的で、現在の加速器技術によれば500億円位の経費で製作できる。もし、その時点までに、ミュオン核融合におけるブレークイーブンが実現していれば、専用加速器による「実用発電炉」も夢ではない。
ミュオン核融合はITERに象徴される熱核融合に比べて、今後の10年を限って考えるかぎり、次の点でユニークで相補的な成果を生み、核融合現象を次世代の原子力エネルギー源として実現するべき歴史的流れに貢献できる。
(1) 連続的に長時間に亘る核融合の実現
ミュオン核融合では、加速器が動き続ける限り核融合が起こり続ける。十分整備された加速器施設では、休止なしで1年を越す核融合の実現が可能である。ITERなどの熱核融合炉ではかなり先になると思われる。
(2) トリチウム燃料の再生産性
実用炉としての核融合炉では、52kg/GW・年程度のトリチウムが必要になる。現在、世界中のトリチウム源は100kg程度であり、核融合現象を用いて再生産を行う必要がある。核融合現象でトリチウムを生むには核融合が圧倒的に小さい領域で起こる事実から考えて、ミュオン核融合の方が有利であろう。
(3) 核融合炉壁の開発
1000cc程の小さな領域でMW(3.5×1017核融合/秒)の核融合が実現されると、3.2×1015n/cm2・s程のフラックスの中性子が標的の表面から放出される。きわめて高強度の14MeV中性子源として利用出来る。熱核融合炉の第1炉壁材料の開発に利用出来る。
(4)「核融合エネルギー」デモ・モデルの実現に向けて
多くの予算、時間、人員を必要とする「核融合エネルギー」の21世紀内での実現には、一般市民の理解と協力を得ることが不可欠である。その意味で、10年以内に、「核融合エネルギー」を市民に見える形で実現し、クリーンで制御可能な形で、kWレベルの核融合エネルギー生産のデモンストレーションがぜひとも必要である。数ある核融合方式の中で、ミュオン核融合が最も可能性があるように思える。図3のような実験設備を用意することにより、10年以内の実現が可能である。